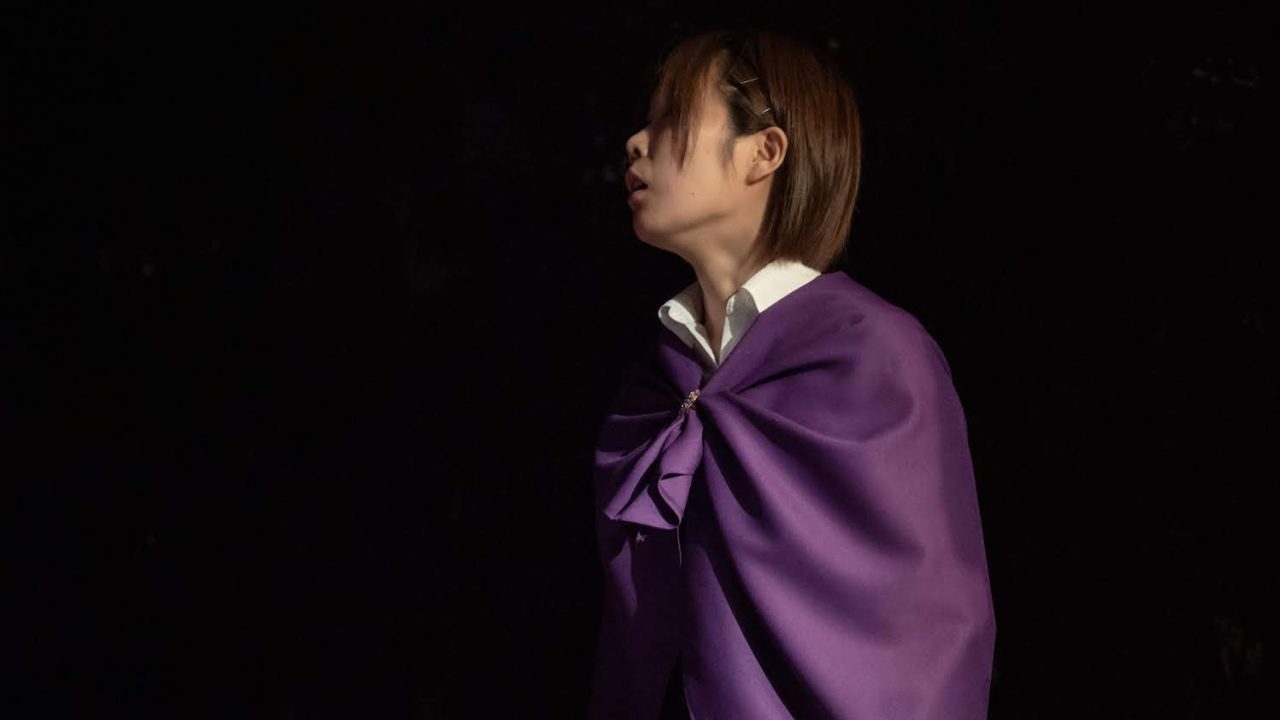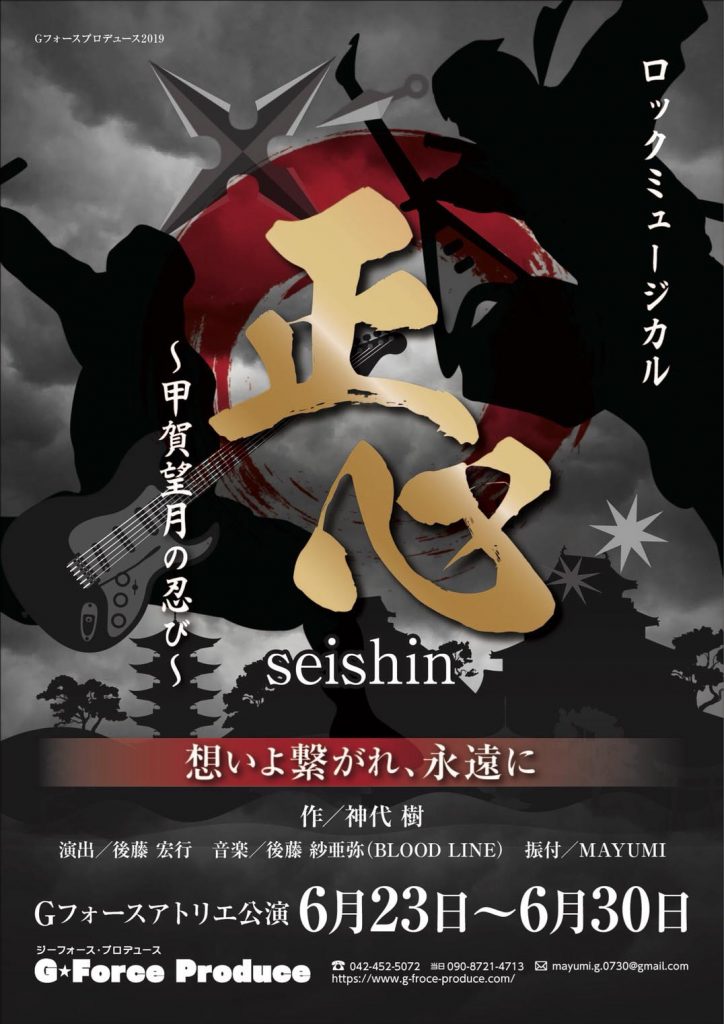梨沢千晴が外部出演いたします!

いつも劇団新和座にご声援いただきましてありがとうございます!!
この度、梨沢千晴が「正心 〜甲賀望月の忍び〜」という舞台に出演させていただくことになりました!
梨沢本人もものすごく気合が入っております!!!
ぜひとも皆様、お運びのほど、ご検討よろしくお願いいたします!
あらすじ
人々を苦しめる闇の衆。
真相を知った甲賀と伊賀、双方の忍びが正心の名の下に立ち上がる。
殺陣あり!歌あり!ダンスあり!
今宵、忍び達のアツイ戦いの幕が切って落とされる!
公演詳細
Gフォースプロデュース2019
正心
〜甲賀望月の忍び〜
スタッフ
作 神代 樹
演出 後藤宏行
音楽 後藤紗亜弥(BLOOD LINE)
振付 MAYUMI
衣装 ちさく
キャスティング 梶島せいな
公演日程
6月
23日14時
24月19時
25火19時
26水14時 19時
27木19時
28金19時
29土14時 18時
30日14時
全10回
チケット料金
¥3.200
前売り・当日共
全席自由席
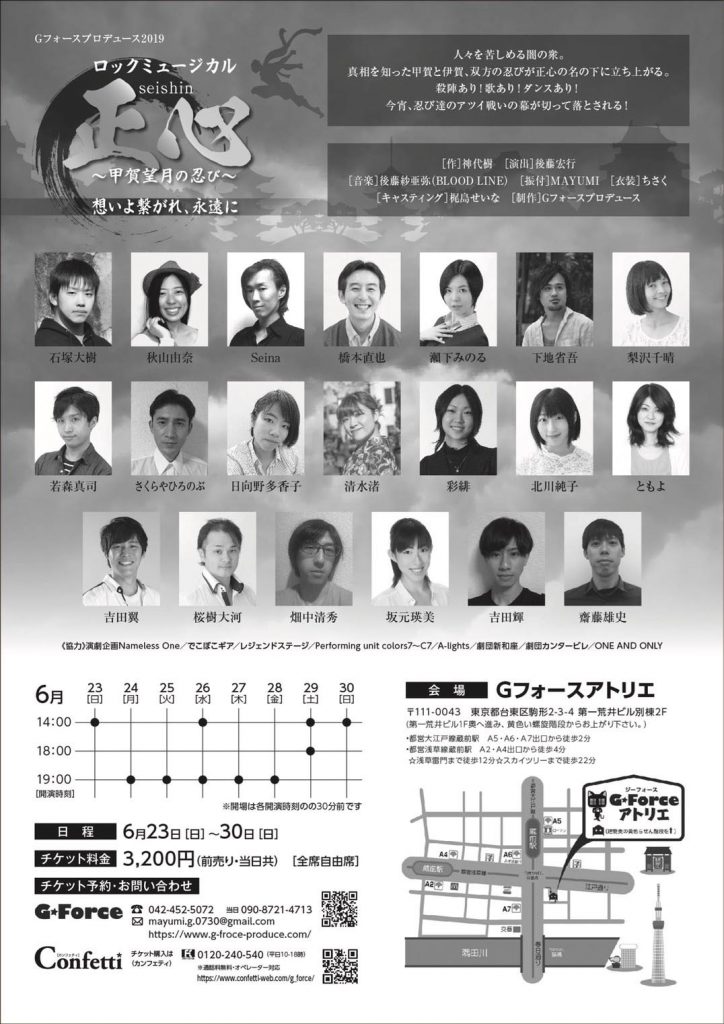
チケットのご予約、お申込み、公演のお問い合わせは
劇団新和座へのメール、(info@shinwaza.com)までお願いいたします。
追加情報などは、このブログでまたお知らせいたします!
梨沢千晴、がんばります!!
どうぞ皆様、ご声援、お運びのほど、よろしくお願いいたします☆☆